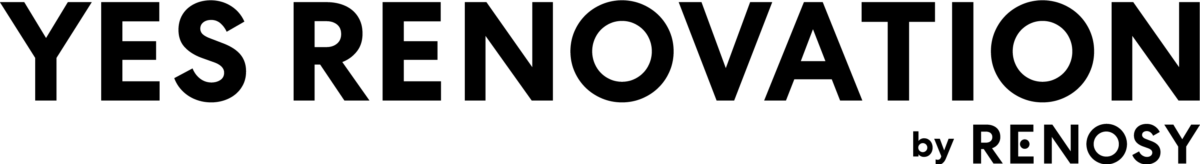デジタル化で進化する賃貸経営|IT重説・電子契約がもたらす3つの変革
デジタル化で進化する賃貸経営|IT重説・電子契約がもたらす3つの変革

近年、不動産業界でも急速に進むデジタル化。
その中でも「IT重説(ITを活用した重要事項説明)」と「電子契約」は、賃貸経営の在り方を大きく変えつつあります。
従来、入居希望者との契約には、対面での説明や紙の契約書が欠かせませんでした。
しかし、オンラインで重要事項の説明を行い、電子署名によって契約を完結できる仕組みが整備されたことで、手続きのスピード化・コスト削減・利便性の向上が実現しています。
これらの新しい制度は、一見すると不動産会社向けの仕組みに思われがちですが、実はオーナー自身の経営効率や入居率にも直結する重要なテーマです。
本コラムでは、IT重説・電子契約の基本から導入メリット、注意点、そしてこれからの賃貸経営のあり方までを詳しく解説します。
不動産業界を変える「IT重説」と「電子契約」とは
国土交通省による規制緩和をきっかけに、賃貸契約の現場でも「IT重説」と「電子契約」が急速に普及しています。
これまで“対面で紙に押印すること”が常識だった契約手続きが、オンライン上で完結するようになり、不動産取引の常識が大きく変わりつつあります。
この章では、それぞれの制度の仕組みと背景、そして不動産業界全体の動きを整理してみましょう。
IT重説とは?導入の背景と法制度の変化
IT重説(Information Technologyを活用した重要事項説明)とは、宅地建物取引業法に基づく重要事項説明を、オンライン上で行うことを認めた制度です。
従来は、宅地建物取引士が入居希望者と同席し、書面を交付して口頭で説明する必要がありました。
しかし、2017年に賃貸借契約において本格的に解禁され、2022年には売買契約にも対象が拡大されるなど、法制度が整備されています。
IT重説では、ZoomやGoogle Meetなどのビデオ通話ツールを用いて、取引士が画面越しに説明を行います。
入居者側は事前に説明資料を受け取り、画面共有を使って内容を確認。やり取りの様子を録画・保存することで、後日の確認にも対応できます。
これにより、遠方に住む入居希望者がわざわざ店舗に出向く必要がなくなり、地方物件への問い合わせにも柔軟に対応できるようになりました。
導入の背景には、社会全体のデジタル化の流れと、新型コロナウイルスの感染拡大があります。
対面接触の制限が求められた時期に、非対面・非接触で契約手続きを進められるIT重説が一気に普及しました。
不動産業界にとっても、業務効率化・顧客満足度の向上を両立できる新しい仕組みとして注目されています。
電子契約とは?紙の契約書からクラウド契約へ
電子契約とは、契約書を紙に印刷せず、電子データとして作成・署名し、オンライン上で締結する方法です。
電子署名法や電子帳簿保存法に基づき、紙の契約書と同等の法的効力を持ちます。
不動産業界では、クラウドサイン、GMOサイン、DocuSignなどの電子契約サービスが広く利用されています。
従来の紙契約では、「印刷→押印→郵送→返送→保管」という手間が発生していました。
特に、契約件数の多いオーナーにとっては、印紙税の支払いや書類管理の負担が大きな課題でした。
電子契約を導入すれば、契約書はクラウド上で即座に署名でき、契約成立までの時間を大幅に短縮できます。
さらに、電子データには印紙税がかからないため、1件あたり数千円のコスト削減につながります。
契約書はクラウド上に安全に保存され、検索・共有も容易です。
万が一のトラブル時にも、契約履歴や署名のログを確認できるため、証拠能力も高いとされています。
また、国税庁の「電子帳簿保存法」改正により、電子データでの保管が正式に認められたことも普及の追い風となりました。
これにより、契約業務全体のデジタル化が一気に進んでいます。
国の後押しと不動産業界全体の動向
国土交通省は、IT重説・電子契約の普及を「不動産取引のデジタル化推進」の柱として位置づけています。
2023年には、電子契約を行う際の運用指針やガイドラインを公開し、各事業者が安心して導入できる環境を整備。
宅建業法上も「書面交付義務」を電子データに代替できるよう明確化が進められました。
大手仲介会社や管理会社では、すでにこの仕組みが標準化されつつあります。
地方の不動産会社や管理会社でも導入が進み、中小規模のオーナーにとっても身近な選択肢となっています。
このように、国の後押しと業界全体の動きが重なり、今やIT重説と電子契約は“あって当たり前”の仕組みへと進化しています。
今後は、契約書だけでなく、更新手続きや退去精算、管理委託契約なども電子化され、賃貸経営の現場におけるペーパーレス化が一層進むと予想されます。
IT重説・電子契約がもたらす賃貸経営の効率化
IT重説と電子契約の導入は、不動産会社だけでなく賃貸オーナーにとっても多くのメリットをもたらします。
契約書類のやり取りがオンラインで完結することで、入居までのスピードが向上し、印紙税や郵送費などのコスト削減も実現します。
さらに、契約情報の一元管理によって業務効率も飛躍的に向上。
ここでは、賃貸経営における具体的な効率化のポイントを3つの観点から詳しく見ていきましょう。
契約手続きのスピード化で“機会損失”を防ぐ
賃貸経営では、「空室期間をどれだけ短くできるか」が収益に直結します。
従来の契約手続きでは、入居希望者との日程調整、郵送による書類のやり取り、対面での説明など、どうしても数日から1週間以上のタイムラグが発生していました。
特に、入居者が遠方在住の場合や、繁忙期に契約が集中する時期は、対応が後手に回るケースも少なくありませんでした。
しかし、IT重説と電子契約を導入することで、これらの手続きが大幅に短縮されます。
重要事項説明はオンラインで即日対応でき、電子契約なら入居希望者が自宅にいながら契約を完結できます。
郵送・押印・返送といったプロセスが不要になり、「決まったタイミングで契約が進められない」という機会損失を防げます。
特に、学生・単身赴任・転勤者など、遠方からの入居者が多い物件では効果が顕著です。
「オンライン対応可」というだけで物件の競争力が上がり、他物件よりも早く入居を決められるケースも増えています。
スピード感を重視する現代の入居者ニーズに応える意味でも、オーナーにとって大きな武器となる仕組みです。
書類保管・管理業務の負担を軽減
賃貸経営では、契約書類や更新書類、保証契約、管理委託契約など、多数の書面を保管する必要があります。
従来は紙の契約書をファイルにまとめ、事務所の棚や倉庫に保管していましたが、年数が経つごとに膨大な量となり、管理が煩雑化するのが課題でした。
また、紛失や破損のリスクも避けられません。
電子契約を導入すれば、これらの契約データはすべてクラウド上で一元管理できます。
契約日・入居者名・物件名などで瞬時に検索でき、必要なときにすぐ閲覧・共有が可能です。
管理会社や税理士といった外部関係者とも、安全に情報共有ができるため、業務連携もスムーズになります。
さらに、電子保管により紙・印刷・ファイル・倉庫などのコストを削減できます。
国税庁が認める「電子帳簿保存法」に対応した管理を行えば、法的にも原本として扱えるため、紙の契約書を残す必要がなくなります。
管理業務が効率化することで、オーナー自身の時間的負担も大幅に軽減されるのです。
印紙税コスト削減と経営の合理化
紙の契約書を作成する際には、契約金額に応じて「印紙税」が課税されます。
たとえば、賃貸借契約書であれば1通あたり2,000円前後が一般的です。
これが年間数十件ともなれば、数万円単位のコストが発生します。
特に複数物件を所有するオーナーにとっては、決して小さな負担ではありません。
電子契約では、紙に印刷して押印するプロセスが存在しないため、印紙税の課税対象外となります。
つまり、電子契約を導入するだけで、同じ契約内容でも印紙税分の節約が可能になるのです。
この「小さな差」が積み重なることで、年間を通じた経費削減効果は非常に大きくなります。
また、電子契約を導入することで、会計処理の自動化や税務対応の効率化も期待できます。
契約データをCSVやPDFで出力すれば、会計ソフトとの連携も容易で、確定申告や年度末の書類整理の手間が格段に減ります。
結果として、経営全体の「コスト構造のスリム化」が実現し、時間・費用の両面で賃貸経営がより合理的になります。
IT重説と電子契約は、単に“便利な仕組み”というだけでなく、オーナー経営における 収益性の向上 と 業務効率化 を両立させるツールです。
スピード化による空室リスクの軽減、ペーパーレス化による管理負担の削減、そして印紙税削減による経費の最適化。
これらの要素はすべて、長期的な賃貸経営の安定化につながります。
導入の際に注意すべきポイントとトラブル防止策
IT重説や電子契約は、利便性が高い一方で、導入・運用の方法を誤るとトラブルの原因になることもあります。
特に法的な要件を満たしていない場合や、通信環境・データ管理に不備があると、契約の有効性が疑われるリスクもあります。
この章では、オーナーが安心して導入するために押さえておきたい注意点と、よくあるトラブル防止策を具体的に解説します。
法的要件の理解と「電子署名」の正しい運用
まず最も重要なのは、「電子契約の法的効力」を正しく理解しておくことです。
電子契約は、電子署名法によって定められた要件を満たしている場合にのみ、紙の契約書と同等の法的効力を持ちます。
この電子署名とは、単なるPDFへのサイン画像ではなく、「本人が契約意思をもって署名したことを確認できる技術的仕組み」を指します。
信頼できる電子契約サービス(クラウドサイン、GMOサイン、DocuSignなど)は、この電子署名法に準拠しており、署名ログの保存やタイムスタンプの発行によって、契約履歴の証拠性を確保しています。
一方で、メールでPDFを送って「承認」と返事をもらうだけでは、法的効力が弱く、後日「契約した覚えがない」と争われるリスクが残ります。
また、宅地建物取引業法上の「書面交付義務」も電子交付が認められるようになりましたが、取引士による本人確認や記録保存のルールが明確に定められています。
こうした法的要件を理解し、正しい方法で運用することが、IT重説・電子契約の信頼性を担保する第一歩です。
通信環境・機器トラブルへの備え
IT重説を実施する際に意外と多いのが、「通信環境」に関するトラブルです。
説明中に映像が途切れたり、音声が聞き取れなかったりすると、入居希望者が内容を十分に理解できず、後日のトラブルにつながる恐れがあります。
国土交通省のガイドラインでも、「通信状態が安定していること」「画面上で書類内容を明確に確認できること」がIT重説の条件とされています。
そのため、不動産会社・オーナー側は、必ず事前に通信テストを行い、説明資料を共有しやすいツール(ZoomやGoogle Meetなど)を選定することが大切です。
また、通信トラブルで説明が中断した場合に備え、録画機能の活用や説明記録の保存を徹底することも推奨されます。
さらに、入居者がスマートフォンのみで参加するケースも増えているため、事前に「推奨デバイス」「通信量の目安」などを案内しておくと親切です。
トラブルを未然に防ぐことで、入居者との信頼関係も維持できます。
データ管理・セキュリティ対策の重要性
電子契約で最も注意すべきなのが、契約データの保管・管理方法です。
契約書には、入居者の個人情報・口座情報・連絡先などが含まれているため、データ流出や不正アクセスが発生すれば、オーナー・管理会社双方の信用に大きなダメージを与えます。
安全に運用するためには、以下の3つのポイントを押さえておく必要があります。
-
信頼できる電子契約サービスを利用すること
ISO27001(情報セキュリティ国際規格)や電子署名法に準拠したサービスを選ぶことで、データの暗号化やアクセス制限が適切に行われます。 -
アクセス権限を限定すること
管理会社やスタッフなど、契約情報にアクセスできる人を最小限に絞り、権限ごとの操作範囲を明確にしておくことが重要です。 -
バックアップと保存期間を明確化すること
電子契約書はクラウド上で安全に保管できますが、万が一に備えて定期的にバックアップを取得しておくと安心です。
また、契約終了後も一定期間(通常は5〜10年)保管義務があるため、保存ルールを明文化しておくと良いでしょう。
これらの対策を講じておけば、個人情報保護法や電子帳簿保存法への対応もスムーズになり、安心して電子化を進めることができます。
入居者への説明不足によるトラブルを防ぐ
IT重説や電子契約は便利な反面、「相手が理解している前提」で進めてしまうとトラブルを招くことがあります。
特に高齢者やデジタル機器に不慣れな入居者にとって、オンラインでの契約は心理的ハードルが高い場合があります。
そのため、事前に「IT重説とは何か」「電子契約の流れ」「署名方法」などを丁寧に案内することが重要です。
メールやLINEで操作マニュアルを送付したり、電話で事前説明を行ったりするだけでも、安心感は大きく変わります。
また、契約締結後には「契約完了メール」や「データ保存方法」を明示し、入居者自身が契約書をいつでも確認できる環境を整えておくことも信頼関係の構築につながります。
IT化が進むほど、“人のフォロー”の価値はむしろ高まります。
デジタルとヒューマンの両面からサポートする姿勢が、円滑な賃貸経営に欠かせません。
IT重説・電子契約の導入には、法的ルールの理解・通信環境の整備・データ管理体制・入居者フォローといった複数の準備が必要です。
しかし、これらをしっかり整えれば、トラブルリスクを最小限に抑えつつ、安全かつ効率的な賃貸経営を実現できます。
導入時は「スピードよりも確実さ」を意識し、信頼できるパートナー(管理会社・システム提供会社)と連携して進めることが成功の鍵です。
デジタル化は「効率化」だけでなく「信頼経営」への一歩
IT重説や電子契約は、単なる業務効率化のツールにとどまりません。
書類の電子化や手続きのオンライン化によって、オーナー・管理会社・入居者の間に生まれる「時間的・物理的な距離」を縮め、よりスムーズで信頼性の高い取引を実現する仕組みでもあります。
これまで賃貸経営においては、「どれだけ迅速に募集・契約を進められるか」が重要視されてきました。
しかし今後は、それに加えて「どれだけ安心して契約できるか」「どれだけ分かりやすく説明されているか」といった“体験の質”が問われる時代に変わっていくでしょう。
また、IT重説や電子契約の導入は、遠隔地の入居希望者にも対応しやすくなるため、入居機会の拡大にもつながります。
地方物件を所有するオーナーにとっては、都市部の入居希望者を取り込むチャンスでもあります。
さらに、書類管理の手間が減ることで、空室対策やリフォーム戦略といった“本来オーナーが注力すべき業務”に時間を割けるようになる点も大きなメリットです。
これからの賃貸経営は、デジタル化を活用して「効率」と「信頼」を両立させることが鍵になります。
IT重説・電子契約を正しく理解し、柔軟に取り入れていくことで、時代の変化に強い経営体制を築くことができるでしょう。