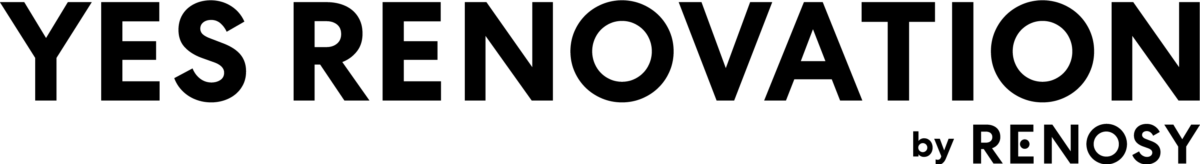賃貸オーナー必見|年末にやるべき節税・経費整理・税務対策
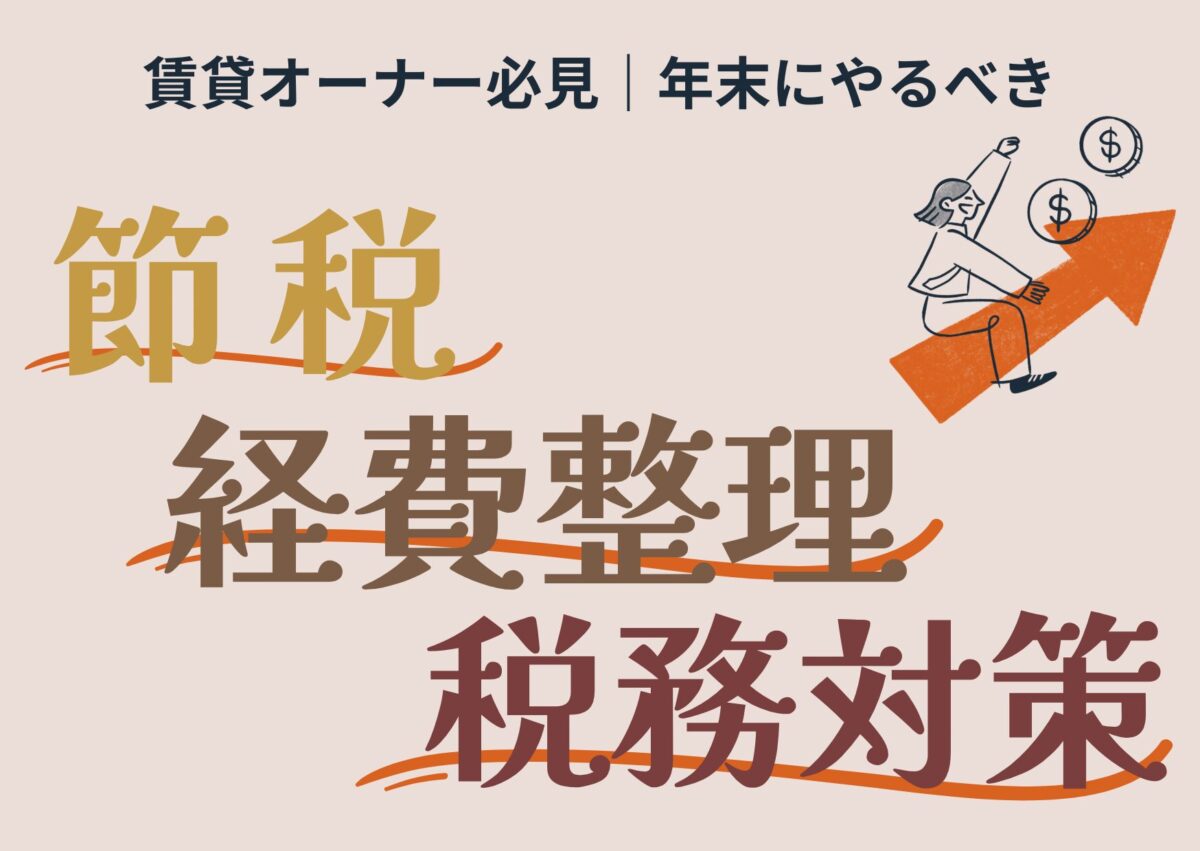
賃貸オーナー必見|年末にやるべき節税・経費整理・税務対策
はじめに|年末は「節税と経営の見直し」を同時に行うチャンス
年末は、賃貸オーナーにとって“税金との向き合い方”を見直す最も重要な時期です。
1年間の収支がある程度見えてくるこの時期に、帳簿を整理し、経費を見直し、支出のタイミングをコントロールすることで、来年の納税額とキャッシュフローを大きく変えることができます。
税務対策というと、「難しそう」「税理士に任せているから大丈夫」と考える方も多いですが、実際にはオーナー自身が“年内にどう動くか”で結果が決まります。
たとえば、修繕を今年中に終えるか、来年に回すか。家族への給与や共済掛金をどうするか――。
これらはすべて、年をまたいでしまうと手遅れになることも。
この記事では、現場で賃貸経営を行うオーナーが、年末に実践すべき税務・節税対策を「すぐにできる行動」に落とし込みながら解説します。
数字に強くなくても大丈夫。
ポイントを押さえれば、税負担を抑えつつ健全な経営を続けるための“仕組みづくり”が見えてくるはずです。
年末に見直すべき「経費と支出」
税務対策は「節税商品を使うこと」からではなく、帳簿を整えることから始まります。
いくら節税ノウハウを知っていても、支出や経費が正しく整理されていなければ、税金は減りません。
年末までの数週間は、領収書や請求書を整理しながら「何を経費にできるか」を一つずつ確認していきましょう。
経費計上の基本ルールと“見落とされやすい支出”
経費計上は、節税の“基本中の基本”。
ところが、実際のオーナーの帳簿を見ていると「本当は経費にできたのに入れていない」支出が多く見られます。
たとえば次のような費用です。
-
管理会社との打合せに行った際の交通費・駐車場代
-
物件確認や現場立会いに行ったときのガソリン代
-
契約書や領収書を保管するためのファイルや文具
-
携帯電話・インターネット代の一部(業務利用分)
-
賃貸経営に関する書籍やセミナー参加費
これらは、業務に関連していれば経費計上が可能です。
ただし、家事との区別がつきにくい支出(たとえば携帯代や車のガソリン代)は、「家事按分(かじあんぶん)」として、業務に使った割合を自分で合理的に決めておくことが大切です。
「おおよそ3割くらいを経費とする」などのざっくりした目安でも、根拠をメモしておけば税務署からの指摘を防げます。
また、電子領収書やPDF請求書などは、紙に印刷する必要はありません。
クラウド会計ソフト(freee、マネーフォワードなど)にデータで保存すれば、電子帳簿保存法にも対応できます。
“領収書をため込まない”ことが、正確な経費計上の第一歩です。
修繕費と資本的支出の線引き|年内にやるべき修繕とは
もうひとつ、年末に見直したいのが「修繕費」の扱いです。
実は、修繕を行うタイミングによって、どの年度の経費にできるかが変わります。
たとえば、入居者退去後の原状回復を12月中に完了して支払いまで済ませれば、今年の経費になります。
しかし、同じ工事でも年明けに着工・支払いすると、翌年分の経費です。
年末が近づくと工務店や内装業者も混み合うため、「支払いが年をまたがないようにする」のがポイント。
請求書日付ではなく、「実際に支払った日」で経費計上できるかどうかが決まります。
また、修繕費と資本的支出(リフォームなどの資産計上)の違いも意識しておくとよいでしょう。
-
壁紙張り替えや水栓交換 → 修繕費として全額経費
-
浴室ユニットバスの入れ替えや間取り変更 → 資本的支出として減価償却
税法上は線引きが曖昧な部分もありますが、「機能を維持する修理」か「価値を高める改修」かが判断基準です。
迷ったときは、業者の見積書に「修繕工事」と明記してもらうだけでも、後々の説明がスムーズになります。
減価償却を活用した節税|タイミングを見極める
減価償却は「時間をかけて経費化する」仕組みですが、ここにも節税のヒントがあります。
中古物件を購入したオーナーの中には、建物の耐用年数を誤って長く設定しているケースが少なくありません。
たとえば、築20年の木造アパートを購入した場合、残りの法定耐用年数は(22年−経過年数×0.8)で計算され、おおむね5〜6年程度になります。
この短い年数で償却できることは、実は大きな節税効果につながります。
また、エアコンや給湯器などの設備をまとめて「建物」として処理している場合も要注意。
これらは「附属設備」として耐用年数が短く設定できるため、見直すだけで経費化のスピードが上がる可能性があります。
もちろん、最終的な処理は税理士に任せればよいですが、オーナー自身が「どの物件がどんな償却スケジュールになっているか」を把握しておくことで、来年以降のキャッシュフローの見通しを立てやすくなります。
年末のタイミングで、税理士から受け取った試算表を眺めるだけでも十分です。
「この建物の減価償却、あと何年残っているんだろう?」と意識することが、次の節税アクションにつながります。
「耐用年数・減価償却」についてはこちらの記事で詳しく解説しています。
オーナーができる“実践的な節税テクニック”
帳簿を整理し終えたら、次は「実際に節税効果を出す行動」です。
税金の世界では、“いつ支払ったか”が非常に重要です。
支出が年をまたぐだけで、経費計上できる年度が変わってしまうため、年末の動き方次第で税額が数十万円単位で変わることもあります。
この章では、12月までに実行できる3つのアクションを押さえていきましょう。
青色申告特別控除の条件を“満たしきる”
青色申告は、個人オーナーにとって最も効果の高い節税制度のひとつです。
65万円(または55万円)の「青色申告特別控除」は、課税所得を直接減らせる強力な仕組みですが、条件を満たしていないと控除額が減ってしまうため、年末にチェックしておく必要があります。
ポイントは以下の3つです。
-
複式簿記で帳簿をつけていること
→ 会計ソフトを使えば自動で対応可能。手書き帳簿はNG。 -
貸借対照表と損益計算書を添付して確定申告していること
→ 帳簿が途中で止まっている人は、今のうちに入力を完了させましょう。 -
電子申告(e-Tax)または電子帳簿保存をしていること(65万円控除の条件)
→ 紙提出だと控除が55万円に減ります。
もしまだe-Taxを使っていない場合は、マイナンバーカード方式かID・パスワード方式で事前登録を済ませておくことが大切です。
年明けに慌てて準備すると間に合わないことも多いので、年内にログイン確認をしておくだけでも安心です。
さらに、家族に手伝ってもらっている場合は、「専従者給与」として経費にできます。
この給与は実際の支払いが条件なので、「年内に振り込んでおく」ことが節税のポイント。12月にまとめて支払っても構いません。
“年内支出”で経費にできるものを前倒し
節税の王道は、「経費を先に支払う」ことです。
現金主義ではなくても、支払いが完了した時点で経費にできる項目が多いため、今年中に支払えるものは前倒ししておくと効果的です。
たとえば次のような支出が対象になります。
-
来年実施予定の修繕・清掃費の一部前払い
-
管理会社への報酬・委託料
-
火災保険・地震保険の一括払い(複数年契約でも可)
-
不動産ポータルサイトの広告費・仲介手数料
-
税理士・司法書士・コンサル費用
火災保険などの「長期契約」は、支払い時に全額を経費にできないケースもありますが、支払時期を調整することで翌年の所得を抑えられる点は同じです。
また、複数物件を持つオーナーの場合、年末にまとめて「共用部の蛍光灯交換」「植栽剪定」「看板清掃」などの軽微な作業を発注しておくのもおすすめです。
小さな経費の積み重ねでも、税率が30%とすれば10万円の経費で3万円の税金削減につながります。
一方で、「節税のためだけに無駄な支出をする」のは本末転倒です。
修繕・広告・共済など、“来年も必要になる支出”を年内に前倒しすることが賢い戦略です。
個人オーナーが使える“控除制度”をフル活用
経費を増やすだけでなく、所得控除を活用して税金を減らす方法もあります。
特に個人オーナーにおすすめなのが、以下の3つです。
① 小規模企業共済
個人事業主や会社役員が加入できる「退職金の積立制度」です。
掛金(月1,000円〜7万円)は全額が所得控除になり、節税効果は非常に高いです。
たとえば年間84万円を積み立てると、所得税・住民税で約20万円前後の節税効果が見込めます。
加入手続きは商工会議所や金融機関で行え、12月中に申込・初回振込をすればその年の控除対象になります。
② iDeCo(個人型確定拠出年金)
こちらも掛金全額が所得控除になります。
投資信託などを活用するため運用リスクはありますが、将来の年金づくりと節税を同時に進められる点が魅力です。
ただし、掛金引き落としのタイミングに注意。12月分が翌年処理になることもあるため、早めの手続きが鉄則です。
③ ふるさと納税
もはや定番の節税策ですが、年末ギリギリまで使える最後の控除制度です。
確定申告で寄附金控除を受けられるほか、「ワンストップ特例制度」を使えば確定申告不要。
寄附額の目安を年収と控除限度額シミュレーションで確認し、12月31日までにクレジット決済を済ませておきましょう。
これらの制度は、「支出をしながら将来の備えにもなる」点が大きなメリットです。
単に経費を使うよりも、資金を残しながら節税できるため、年末のキャッシュマネジメントにも役立ちます。
来年に備える「長期的な税金対策」
節税は「年末だけの一発勝負」ではありません。
短期的に税金を減らすことに集中しすぎると、翌年以降の資金繰りや将来の資産承継に悪影響を与えることもあります。
年末のこの時期こそ、来期以降を見据えた中長期的な税務戦略を練る絶好のタイミングです。
法人化や相続対策といった“次の一手”も意識して、継続的に安定した賃貸経営を目指しましょう。
税務調査に備える“帳簿管理術”
税務調査では、帳簿や領収書の整備状況が最初に確認されます。
特に個人オーナーの場合、家事関連支出と業務経費の線引きがあいまいだと「私的利用ではないか」と指摘されやすい傾向があります。
まず基本は、レシート・領収書を日付順に保管し、摘要欄を具体的に記入すること。
たとえば「ガソリン代」ではなく「〇〇物件現地確認用」など、業務目的が明確になるようにしましょう。
近年はクラウド会計ソフトを活用すれば、領収書の写真をアップロードするだけで自動仕訳が可能です。
紙の束をため込むよりも、検索性が高く効率的です。
また、「家事按分」の説明も重要です。
たとえば自宅兼事務所の場合、面積比(例:全体の20%を事務使用)や使用時間比で合理的に按分し、算定根拠をメモしておくと、調査時にスムーズに説明できます。
なお、税務調査で指摘されやすい経費トップ3としては、
①自家用車のガソリン代・車検費用
②飲食・交際費
③通信費(スマートフォンやネット回線)
が挙げられます。
いずれも「業務との関連性」を証明できる資料(入居者対応履歴、物件訪問記録、打合せ日程など)を残しておくことが、最大の防御策です。
法人化の検討は「利益額」と「家族構成」で判断
節税の観点から注目されるのが「法人化」です。
個人として賃貸経営を続けている場合、所得が増えるほど累進課税で税率が上がる仕組みになっています。
目安として課税所得が800万円を超えるあたりから、法人化を検討する価値が出てきます。
法人化すれば、
-
法人税率が約23%前後で一定(所得税の最高税率55%に比べると低い)
-
役員報酬として家族に給与を支払うことで所得分散が可能
-
社会保険の活用や退職金制度を設けることで長期の節税設計ができる
といったメリットがあります。
一方で、法人設立には設立費用や会計事務所の顧問料、社会保険料の負担なども発生します。
そのため、「利益規模」と「家族構成(給与分散の余地があるか)」をもとに総合判断することが大切です。
特に、配偶者や子どもが実際に物件管理や入居対応を行っている場合は、役員登用して給与を支給することで所得分散がしやすくなります。
法人化は単なる節税策ではなく、家族の将来も見据えた“事業承継の第一歩”として位置づけるとよいでしょう。
将来の相続・贈与を“今のうちに軽く試算”
長期的な税務戦略の中で、もう一つ見逃せないのが「相続・贈与対策」です。
特に不動産オーナーの場合、現金よりも評価額の高い資産を持っているため、相続発生時に思わぬ税負担が生じることがあります。
まずは、自分の所有物件の固定資産税評価額を市区町村の課税明細書や法務局の登記簿で確認しておきましょう。これが相続税評価の基礎となります。
可能であれば、税理士に依頼して簡易試算をしてもらうのもおすすめです。
現在の資産状況を“見える化”することで、贈与のタイミングや名義変更の方針が立てやすくなります。
また、家族共有名義にする場合は注意が必要です。
持分割合を明確にしておかないと、後に売却や相続の際にトラブルが生じる可能性があります。
登記名義・負担割合・家賃収入の受け取り方を一貫させておくことが肝心です。
相続や贈与は「早く手を打つほど選択肢が増える」分野です。
年末の今こそ、税理士や司法書士に相談し、5年・10年先を見据えた資産承継プランの第一歩を踏み出す時期といえるでしょう。
年末の節税は“未来への経営戦略”
年末の税務戦略は、単なる「節税テクニック」ではなく、来年以降の賃貸経営をスムーズに進めるための“準備期間”でもあります。
経費の整理や修繕の時期調整といった短期的な工夫に加え、帳簿管理の徹底・法人化の検討・将来の相続準備など、長期的な目線で税務を捉えることが重要です。
支出を正しく分類し、必要経費を確実に計上することで、現金の流れを安定させつつ税負担を最適化できます。
また、税理士との定期的な相談や会計ツールの活用により、経営判断の精度も向上します。
節税とは「税を減らすこと」ではなく、「経営を健全に保つための戦略的コントロール」です。
年末の今だからこそ、足元を整理しながら来年・再来年を見据えた税務計画を立てていきましょう。