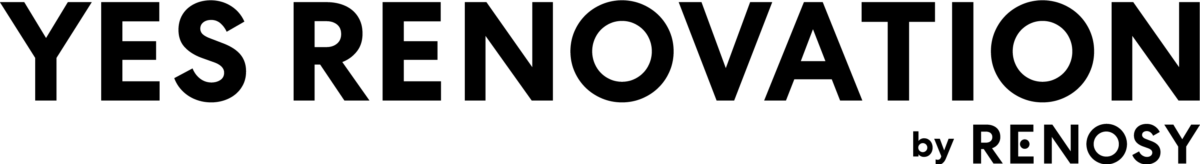家賃滞納が起きたらどうする?|オーナーが最初の30日で取るべき行動マニュアル

家賃滞納が起きたらどうする?|オーナーが最初の30日で取るべき行動マニュアル
賃貸経営において「家賃滞納」は、オーナーであれば誰しもが直面する可能性があるトラブルです。
長期的に安定した入居者ばかりであっても、突発的な失業や病気、家庭の事情などにより、ある日突然「家賃が入金されない」という事態は起こり得ます。
現在、多くの賃貸物件では 保証会社を利用した賃料保証 が一般的になっています。
そのためオーナーの中には「保証会社があるから、滞納があっても自分は関係ない」と考える方も少なくありません。
確かに保証会社が立て替え払いをしてくれる仕組みは強力で、かつてのように「入居者に直接取り立てを行う」ような負担は大幅に減りました。
しかし実際の現場では、保証会社に任せきりにしてはいけない ケースが多く存在します。理由は大きく分けて3つあります。
-
保証対象外となるリスク
保証会社によっては「報告の遅れ」や「特定の契約条件」次第で、立替払いが適用されないことがあります。 -
繰り返し滞納による管理コスト増
一度滞納が発生した入居者は、その後も同じ行動を繰り返す傾向があります。保証会社が立替払いをしてくれるからといって放置してしまうと、管理会社やオーナーの負担が増え、退去や訴訟に発展することもあります。 -
入居者トラブルの長期化
家賃滞納は、しばしば「孤独死」「夜逃げ」「物件の放置」など、より深刻な問題の前兆となることもあります。早期に異変を察知することで、被害を最小限に食い止められる可能性が高まります。
つまり「保証会社がある=安心」ではなく、オーナー自身が30日以内に正しく対応できるかどうか が、結果的に物件の安定経営に大きく影響します。
このコラムでは、滞納が発生してから30日以内にオーナーが実際にできる対応策を、3つのステップに分けて解説します。
まずは「発生日〜7日以内」にやるべき初動対応から見ていきましょう。
滞納発生から7日以内にやること
滞納が発生してからの最初の7日間は、初動対応のゴールデンタイムです。
ここで適切に動けるかどうかが、その後の保証会社の対応スピードや入居者への心理的プレッシャーに直結します。
特に保証会社との報告のタイミングを誤ると、立替払いの対象外になるリスクもあるため注意が必要です。
入居者との直接的なやり取りは管理会社に任せつつ、オーナーは『確認・報告・記録』を徹底することが、トラブルの長期化を防ぐ鍵となります。
入金確認を確実に行う
まず重要なのは「本当に滞納なのかどうか」を正しく把握することです。
システムの入金反映の遅れや、単なる振込日勘違いなどのケースも珍しくありません。
-
賃料振込口座の入金確認を日付単位で行う
-
オンライン管理システムを利用している場合はリアルタイムで確認
-
共同名義の物件では、家族や共同経営者と情報を共有する
“勘違い滞納”と“本格的な滞納”を早期に区別すること が、その後の対応スピードを左右します。
管理会社・保証会社に即時連絡
滞納が発覚したら、まずは管理会社に報告し、その後保証会社へ連携することが基本です。
ここで注意すべきは、「報告の遅れが保証対象外につながるリスク」 です。
保証会社によっては、
-
滞納から14日以内に報告すること
-
報告を受けてから保証会社が立替を開始すること
といった条件が契約書に明記されています。オーナーが「まあ数日遅れても大丈夫だろう」と考えてしまうと、後々「保証が下りない」という事態になりかねません。
このため、滞納を確認した時点で 即日で管理会社に報告するフロー を定めておくことが重要です。
入居者への一次連絡(基本は管理会社対応)
オーナーが直接連絡を取る必要は基本的にありません。
むしろ、個別に電話や訪問をしてしまうと、
-
感情的なトラブルに発展する
-
言った・言わないの証拠が残らない
といったリスクがあります。
一次連絡は、原則として管理会社が行い、保証会社に記録を残すのがベストです。
ただし、オーナーとして把握しておくべきことは、「どういう文面・口調で入居者に連絡するのか」 という点です。
たとえば初期段階では、「催促」というより「確認」に近いニュアンスで伝えることが一般的です。
柔らかいトーンでの一次連絡は、単なるミスやうっかり忘れの場合にトラブルを悪化させず、早期解決につながります。
初動段階でオーナーが把握すべき情報
7日以内の初動で、オーナーが管理会社から確認しておきたいポイントは以下の通りです。
-
入居者の連絡がついたかどうか
-
入居者からの回答内容(うっかり忘れ、資金難、体調不良など)
-
今後の入金予定日が示されているか
-
保証会社への報告が済んでいるか
この時点で「今月中には払えそう」と回答があれば様子を見ることも可能ですが、「支払いの見込みが立たない」「そもそも連絡がつかない」 という場合には、早めに次のステップに進む必要があります。
7日以内対応のまとめ
-
入金確認は日付単位で徹底する
-
滞納発覚後は管理会社・保証会社に即日報告
-
一次連絡は管理会社に任せ、オーナーは経過を共有してもらう
-
連絡がつかない場合は、次の「書面催告・保証会社本格対応」に備える
このように、最初の7日間は「事実確認」と「早期連絡」が鍵 となります。
ここでの動きが遅れると、保証対象外になるリスクや、入居者トラブルの長期化を招くことになります。
7日〜14日以内にやること
滞納が発生してから最初の1週間で「入金確認」や「保証会社への報告」を済ませたあとは、次のステップに進みます。
7日〜14日の間は、保証会社が本格的に動き始めるタイミングでもあり、オーナーとしては 「進捗の確認」と「役割分担の明確化」 がポイントになります。
ここで状況を把握せずに放置してしまうと、思わぬトラブルにつながることがあるため注意が必要です。
保証会社の立替処理の仕組みを把握する
家賃保証会社の多くは、滞納が発生してから一定期間経過後に「立替払い」を行います。
一般的には 賃料の入金日から数日〜1か月程度のラグ があります。
例えば、毎月5日が家賃の支払日だとすると、入居者が未払いのまま7日を過ぎると、保証会社は「滞納」と認定し、10日〜15日頃にオーナーへ立替入金するケースが多いです。ただし、会社ごとに立替のタイミングは異なります。
-
即日立替型(支払期日からすぐにオーナーへ入金)
-
月1回まとめて立替型(毎月●日に立替分をまとめて入金)
この仕組みを知らないと、「まだ入っていないけど大丈夫なのか?」と不安になったり、「保証会社が対応していないのでは?」と誤解してしまうことがあります。
契約書や管理会社への確認を通じて、自分の契約がどの立替方式なのかを正確に把握しておくこと が重要です。
書面通知の有無をチェックする
保証会社は、滞納が確認されると入居者に対して「催告通知」を送るのが一般的です。
これは督促状に近いもので、いつまでに支払わなければ保証契約が解除される可能性がある といった強い文面が盛り込まれているケースもあります。
オーナー自身がその通知文を受け取ることは少ないですが、管理会社や保証会社に確認すれば、どのような内容を送付したのかを知ることができます。
通知が出ていれば、入居者への心理的なプレッシャーが働きますし、今後の対応を予測するうえで参考になります。
ここで大切なのは、オーナーが直接入居者に連絡を重ねすぎないこと です。
保証会社の業務とバッティングしてしまうと、「二重請求」や「言った・言わない」のトラブルに発展する恐れがあります。
通知の有無や内容を把握したうえで、基本的には保証会社の動きに委ねるのがベストです。
管理会社と保証会社の役割分担を明確にする
滞納対応では、管理会社と保証会社の両方が関わります。
しかし、誰がどの範囲まで対応するのかは契約内容や会社ごとに違いがあります。
たとえば、
-
管理会社:入居者への一次連絡・近隣対応・オーナーへの報告
-
保証会社:入居者への督促・立替入金・法的手続き準備
といった分担が一般的です。
ただし、管理会社によっては「督促はすべて保証会社に任せています」と明言するところもあれば、「うちは入居者と直接やりとりします」とするところもあります。
ここを曖昧にしたままにすると、オーナーが「どこまで任せて良いのか」を判断できず、不必要な不安を抱えたり、逆に放置してしまうリスクがあります。
オーナーとしては、管理会社に対して必ず確認しておくべき質問は以下のとおりです。
-
保証会社と管理会社、どちらが入居者に直接コンタクトを取るのか?
-
立替後の滞納分の回収は誰が責任を持つのか?
-
法的手続きに進む場合、どちらが主導して進めるのか?
こうした確認を7日〜14日の間に済ませておけば、30日を超えて長期化した場合にも慌てずに対応できます。
「進捗の見える化」で安心感を得る
滞納対応は、一度発生するとどうしても心理的なストレスを伴います。
「今どうなっているのか」「このまま支払ってもらえるのか」という不安は、特に初めて経験するオーナーにとって大きな負担です。
この時期にオススメなのが、進捗の見える化です。
管理会社や保証会社に対して「現在の対応状況を月1回でいいので報告してほしい」と依頼しておくだけでも、安心感が大きく違います。
メールや報告書の形で残してもらえれば、後から「対応が遅かったのでは?」といった不信感も防げます。
次のステップに備えるための準備期間
7日〜14日以内は、「保証会社の動きを把握し、役割分担を明確にする」ことが最大のポイントです。
この期間で必要な確認を済ませておけば、オーナーとしては余計な不安を抱えることなく、保証会社や管理会社に任せられる体制が整います。
逆にこの段階で放置すると、「誰が責任を持つのか」が曖昧になり、長期滞納やトラブルの温床になりかねません。
15日〜30日以内にやること
滞納が発生してから2週間を過ぎても入金が確認できない場合、事態はより深刻化していきます。
ここからの15〜30日の間は、単なる「一時的な支払い遅延」ではなく、長期滞納や契約違反へ発展するリスクが高まる期間です。
オーナーとしては、保証会社に任せる部分と自ら確認すべき部分を切り分け、将来的な法的対応を見据えて準備を整えることが重要になります。
「繰り返し滞納」の兆候を見逃さない
15日を過ぎても入居者が支払わない場合、単なる一度きりの遅延ではなく「常習的な滞納」へ発展する可能性があります。特に以下のような兆候が見られる場合は注意が必要です。
-
支払い遅れが毎月続いている
-
分割払いの相談を頻繁に持ちかけてくる
-
連絡が取れなくなることが多い
保証会社が立替をしているため、オーナーには直ちに金銭的損失が出ないこともあります。
しかし、滞納を繰り返す入居者は退去や訴訟につながるリスクが高いため、早めに管理会社・保証会社と方針を共有しておくべきです。
証拠の保全を始める
この時期に最も重要なのが「証拠の保全」です。
保証会社が法的手続きに進む場合や、オーナー自身が訴訟・強制退去を検討する場合、やり取りの記録が極めて重要になります。
具体的には:
-
管理会社からの報告メールを保存
-
保証会社の通知書や催告状をコピー
-
入居者からの電話やメールの内容をメモに残す
これらは将来的に「滞納が継続していた事実」を証明する資料となり、裁判や調停の場で大きな効力を発揮します。
逆に、証拠がなければ「本当に督促していたのか?」と不利な立場になる恐れがあります。
保証会社との連携を強化する
30日近く経過しても解決しない場合、保証会社は「今後の対応」を本格的に検討し始めます。
たとえば:
-
今後も立替を継続するのか
-
契約解除や明渡訴訟を視野に入れるのか
-
分割払いなど入居者との和解案を検討するのか
この段階でオーナーが受け身の姿勢を取ってしまうと、保証会社の判断だけで物事が進んでしまい、結果的に「退去になって空室リスクが増える」といった不本意な展開につながることもあります。
オーナーとしては「どの選択肢が自分の物件経営にとって最善か」を踏まえて意見を伝えることが大切です。
法的対応を見据えた心構え
滞納が30日を超えると、保証会社や管理会社は法的手続きの準備に入る可能性があります。
オーナー自身が直接訴訟に関与する場面は少ないものの、以下の点は理解しておきましょう。
-
明渡訴訟は解決までに数か月かかる
-
訴訟費用や弁護士費用は保証契約により負担の有無が異なる
-
強制退去になった場合、原状回復費や残置物処理費がかかる
つまり、滞納が長期化すればするほど「経済的損失のリスク」が大きくなるということです。
保証会社が費用を負担してくれる場合もありますが、オーナーとしては「最悪のシナリオ」も頭に入れて経営計画を見直しておく必要があります。
次のステップに備える30日間
15日〜30日の期間は「解決が見えないまま長期化するかどうか」を分ける重要なフェーズです。
ここで証拠の保全や保証会社との連携を強化しておけば、その後の法的対応や退去リスクにも落ち着いて対処できます。
逆に放置してしまうと、気づけば数か月滞納が続いていた…という事態になりかねません。
オーナーとしては、この30日間を「次のステップに備える準備期間」として位置づけ、主体的に動くことが求められます。
保証会社が付いていない場合の初動マニュアル
現在では、多くの賃貸契約に保証会社が導入されています。
しかし、すべての入居者が保証会社付きというわけではありません。
古くから住んでいる入居者や、法人契約・親族保証を条件とした入居の場合など、保証会社が関与していないケースも依然として存在します。
オーナーにとっては少数派とはいえ、万が一そのような入居者で滞納が発生した場合には、自ら初動を取らなければならない点に注意が必要です。
初動はスピード重視
保証会社がない場合、滞納発生からの初動対応は特にスピードが重要です。
まずは「支払忘れ」なのか「支払い能力がない」のかを見極める必要があります。
-
電話連絡:できるだけ早く入居者本人に連絡し、事情を確認
-
書面通知:電話がつながらない場合は、督促状を郵送(簡易書留が望ましい)
-
訪問確認:管理会社があれば同行して居住実態を確認
この段階で「一時的な遅れ」と「深刻な滞納」を切り分けられるかどうかが、その後の対応スピードを決めます。
書面による正式な催告
連絡をしても改善が見られない場合、内容証明郵便による催告状の送付を検討します。
これは「法的手続きに進む前段階の通知」として有効であり、入居者に強いプレッシャーを与える効果があります。文面には、
-
滞納している金額
-
支払い期限(通常は7日程度)
-
期限までに支払いがなければ契約解除も検討する旨
を明記することが重要です。
専門家への早期相談
保証会社がない場合、30日を超えても支払いがなければ、オーナーだけで解決するのは難しくなります。
ここで大切なのは「早めに専門家へ相談する」ことです。
弁護士や司法書士であれば、
-
支払督促の申し立て
-
少額訴訟(滞納額が60万円以下の場合)
-
明渡訴訟の準備
といった法的手続きを視野に入れた対応を提案してくれます。
対応が遅れると、滞納額が膨らむだけでなく、物件が長期間収益を生まない状態に陥ってしまいます。
自力での解決は避ける
保証会社がいないと「家賃を取り戻したい」「早く退去させたい」と焦る気持ちが強くなりますが、オーナーが自力で強引に入居者を追い出すことは法律で禁止されています。
無断で鍵を交換したり、荷物を処分する行為は「不法行為」とされ、逆に損害賠償を請求される恐れもあります。
必ず、法的に正しい手順を踏むことを心がけましょう。
少数派だが備えは必要
保証会社なしでの滞納は、全体の中では少数派かもしれません。
しかし、長期入居者や古い契約形態では今なお存在し得るリスクです。
「自分の物件に保証会社なしの入居者がいないか」を確認し、もし対象者がいる場合には「滞納が発生したらどう動くか」をシナリオ化しておくことが大切です。
備えがあるかどうかで、対応スピードと損失の大きさは大きく変わります。
初動30日で勝負が決まる
家賃滞納は、賃貸経営において誰にでも起こり得るトラブルです。
しかし、そのダメージを最小限に抑えられるかどうかは、オーナー自身の「最初の30日間の動き方」にかかっています。
今回ご紹介したように、滞納発生から30日以内には明確なステップがあります。
-
0〜7日以内:入金確認と保証会社への即報告。ここでの対応遅れが、保証対象外リスクを招く。
-
7〜14日以内:保証会社・管理会社との役割分担を確認し、進捗を「見える化」して不安を減らす。
-
15〜30日以内:繰り返し滞納や長期化の兆候を察知し、証拠を保全。保証会社との連携を深め、最悪のケースに備える。
この3段階を踏むことで、オーナーは「放置するリスク」から解放され、トラブルの長期化を防ぐことができます。
保証会社があるからといって油断は禁物
多くのオーナーにとって、保証会社の存在は大きな安心材料です。
しかし、「保証会社があるから放置していい」わけではない点を忘れてはいけません。
保証会社が立替をしてくれるとはいえ、入居者が繰り返し滞納すれば退去リスクや空室損失に直結します。
オーナーとしては「お金は入ってくるから問題なし」ではなく、物件の安定経営を守るために滞納リスクを管理する視点を持つことが大切です。
保証会社なしのケースも想定しておく
今回、最後に少しだけ触れた「保証会社が付いていない場合の初動マニュアル」も忘れてはならないポイントです。
古い入居者や法人契約、連帯保証人による契約など、少数ながら今も存在する形態です。
もしその入居者が滞納したら、オーナー自身が主体的に動かざるを得ません。
「万一のとき、どう動くか」をシナリオ化しておくことが備えになります。
経営視点での最終チェック
最後に、オーナーが自分の物件経営を振り返る際にチェックしておきたい視点を整理しておきます。
-
自分の物件の入居者は全員、保証会社付き契約か?
-
保証会社の立替タイミングと役割を正確に把握しているか?
-
管理会社と保証会社、それぞれにどこまで任せられるか明確か?
-
証拠保全の仕組み(メール保存、報告書保管など)は整っているか?
これらを確認しておけば、実際に滞納が発生しても慌てず、冷静に対応できるはずです。
おわりに
家賃滞納は、オーナーにとって精神的にも経営的にも大きなストレスを与える問題です。
しかし、最初の30日で正しい対応を取れば、その影響は大幅に軽減できます。
保証会社や管理会社に丸投げするのではなく、オーナー自身が「確認」と「判断」の役割を果たすことが、賃貸経営を安定させる最大のポイントです。
「備えあれば憂いなし」。
滞納が起こってから慌てるのではなく、平時から保証会社や管理会社との連携を強化し、万が一の際に動ける体制を整えておきましょう。