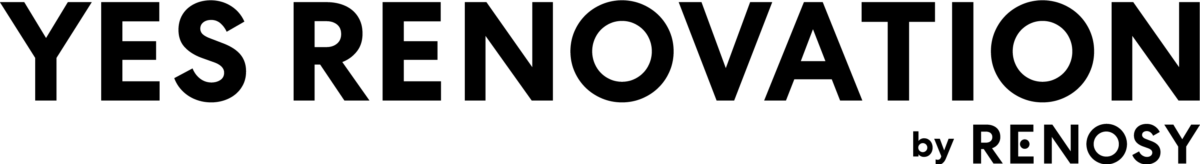【知って得する!】リノベーションの耐用年数・減価償却とは?

不動産投資を行う際、多くのオーナーが最初に注目するのは「利回り」や「家賃収入」です。
確かに、毎月の収入が安定しているかどうかは経営を続けていくうえで重要な指標です。
しかし、賃貸経営は単なる収支計算だけでは語れません。特に日本では、税制上の仕組みをどう活用するかが投資の成否に直結します。
その中でも中心的な役割を果たすのが「減価償却(げんかしょうきゃく)」という会計上の考え方です。
減価償却は、不動産投資を始めたばかりの方にとっては少し難解に感じられるかもしれません。
けれども、これは単なる税務上のルールではなく、キャッシュフローを安定させるための強力な武器です。
特に中古物件を購入する投資家にとって、減価償却を理解し、適切に使いこなすかどうかで「投資効率」が大きく変わってきます。
たとえば、同じ1億円の物件を購入した場合でも、構造や築年数によって耐用年数が異なり、毎年計上できる減価償却費の額も変わります。
その結果、同じ家賃収入を得ていても、オーナーが手元に残す資金(キャッシュフロー)には大きな差が生まれるのです。
不動産投資における成功のカギは、単に物件を安く買うことや満室経営を続けることにとどまりません。
税制を味方につけ、利益をどのようにコントロールするかを理解することが、長期的に資産を増やすうえで不可欠です。
本稿では、減価償却の基本的な考え方から、不動産投資における具体的な活用方法、さらに注意すべきポイントまでを体系的に解説していきます。
減価償却とは何か:基本の考え方を理解する
減価償却とは、建物や設備といった「時間の経過とともに価値が減少する資産」について、その減少分を費用として毎年少しずつ計上していく会計処理のことです。
たとえば、新築の建物を購入した場合、その価値は購入直後から少しずつ下がっていきます。
外壁は劣化し、内装も古くなり、いずれは修繕や建て替えが必要になります。
このように資産が時間とともに消耗していくのは自然なことです。
しかし、会計上は「購入した年に一括で費用化」してしまうのではなく、法律で定められた耐用年数に従って分割計上していきます。
これが減価償却です。
対象となる資産
不動産投資において減価償却の対象となるのは、土地を除いた建物部分および附属設備です。
土地は時間が経っても基本的には価値が減らないとされているため、減価償却の対象外となります。
一方、建物(木造・鉄骨造・RC造など)や、エレベーター・給排水設備・空調設備などは、耐用年数に応じて償却していきます。
また、購入時にかかった仲介手数料や登記費用の一部、リフォーム費用なども、資本的支出と認められれば減価償却の対象となる場合があります。
これらは「一度に全額経費にできるか」「数年にわたって償却するのか」で大きく節税効果が変わるため、判断が重要です。
耐用年数と計算方法
耐用年数とは、国税庁が定める「その資産が利用に耐えるとされる期間」のことです。
たとえば、木造住宅は22年、鉄筋コンクリート造(RC造)は47年など、構造によって一律の基準があります。
中古物件の場合は、法定耐用年数から経過年数を差し引いたり、特例計算を行ったりすることで新しい耐用年数を算出します。
計算方法には主に以下の2種類があります。
-
定額法
資産の取得価額を耐用年数で割り、毎年同じ額を償却していく方法。現在の不動産投資ではこちらが主流です。 -
定率法
残存簿価に一定率を掛けて償却していく方法で、初期に多く、後年は少なく償却する。現在は原則として法人税法上の建物には認められていませんが、古い資産や設備によっては適用例があります。
減価償却の意義
一見すると「単なる会計上の処理」に見える減価償却ですが、不動産投資家にとっては次のような大きな意味があります。
-
課税所得を圧縮できる(節税効果)
償却費は実際の支出を伴わない「非現金支出」でありながら、経費として認められるため、課税対象となる所得を減らせます。 -
キャッシュフローの改善
税金を抑えつつ手元資金を厚くできるため、次の投資や修繕費用に回しやすくなります。 -
資産の実態把握
帳簿上の価値を時間とともに減らしていくことで、資産の現実的な評価に近づけることができます。
このように、減価償却は「節税テクニック」以上の意味を持ち、不動産投資の収益構造を理解するうえで欠かせない仕組みなのです。
不動産投資における減価償却の特徴
不動産投資における減価償却は、他の事業資産に比べて金額規模が大きく、経営に与える影響が非常に大きい点が特徴です。
建物の構造や築年数によって耐用年数が異なるため、同じ価格の物件を購入しても、毎年の償却額は大きく変わります。
特に中古物件の場合、短期間で多額の償却が可能になるケースも多く、投資戦略を立てるうえで欠かせない要素となります。
不動産投資ならではのポイント
減価償却は会計処理全般で使われる概念ですが、不動産投資においては特に注目されます。
理由はシンプルで、建物価格が大きいため、減価償却費も大きな金額になるからです。
車やパソコンのような少額資産であれば、償却による影響は限定的です。
しかし数千万円、数億円の物件を購入した場合、毎年数百万円規模の減価償却費を計上できるケースも珍しくありません。
また、土地部分は償却できないため、購入時に建物価格をどれだけ計上できるかが重要になります。
実務では、売買契約書や固定資産税評価額を基に建物と土地の割合を算定しますが、ここを工夫することで節税効果に差が出ることもあります。
構造別の耐用年数
建物の耐用年数は構造ごとに国税庁が定めています。以下は代表的なものです。
| 構造 | 法定耐用年数 |
|---|---|
| 木造・合成樹脂造 | 22年 |
| 軽量鉄骨造(骨格材厚3mm以下) | 19年 |
| 軽量鉄骨造(骨格材厚3〜4mm) | 27年 |
| 重量鉄骨造(骨格材厚4mm超) | 34年 |
| 鉄筋コンクリート造(RC造)・鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC造) | 47年 |
たとえば木造アパートは22年で償却が終わるため、早いスピードで費用計上でき、短期間で節税効果を享受できます。
一方、RC造マンションは47年と長いため、1年あたりの償却額は少なくなりますが、長期間にわたり安定して費用計上できるメリットがあります。
中古物件の取り扱い
中古物件を購入した場合は「法定耐用年数からの計算」がポイントになります。
新築とは異なり、既に経過している年数を考慮して、新しい耐用年数を再計算します。
国税庁のルールでは、
-
法定耐用年数の全部を経過していない場合:
「法定耐用年数 − 経過年数」+「経過年数 × 20%」 -
法定耐用年数を超えている場合:
「法定耐用年数 × 20%」
が新たな耐用年数になります。
例えば、築20年の木造アパート(法定耐用年数22年)を購入した場合:
-
法定耐用年数(22年)− 経過年数(20年)=2年
-
経過年数20年 × 20%=4年
-
新耐用年数=2年+4年=6年
となり、残り6年間で建物価格を全額償却できることになります。
これが「中古物件の減価償却が節税に有利」と言われる理由です。
投資家が注目する理由
こうした仕組みにより、中古一棟アパートや築古RC物件は投資家に人気があります。
購入後数年間で大きく減価償却を取り、税金を圧縮しながらキャッシュフローを確保する狙いです。
特に高所得者や法人経営者が節税目的で中古物件に注目するのは、この減価償却のインパクトが大きいためなのです。
リノベーションの際のポイントや考え方
リフォームやリノベーションを行った場合、その費用は「資本的支出」か「修繕費」のどちらかに分かれます。
下記のポイントで見極められますが、それぞれの判別方法には厳密な定義はありませんので、リノベーションを行う前に税理士などのプロと相談されることをおすすめします。
資本的支出とは
資本的支出とは、固定資産の修理や改良のために支出した費用のうち、その資産の耐久性を高め、価値を向上させた部分に対応する金額のことをいいます。
リフォーム・リノベーション費用が資本的支出と判断された場合、減価償却費として計上することができます。
資本的支出の具体例
- 工事費用が20万円を超えるもの
- 元の状態より価値を高めたもの
- 販促を目的とした改装や増築・設備の追加
- 災害に備えて設備を強化・追加した場合
修繕費とは
一方で修繕費とは、固定資産を修理や改良のために支出した費用のうち、その資産の通常の維持管理、もしくは、その資産が毀損したために行う原状回復を目的として支出したと認められる部分の金額のことをいいます。
退去後の原状回復工事などの簡単なリフォームの費用は「修繕費」として経費処理されるため、減価償却を行う必要はありません。
修繕費の具体例
- 工事費用が20万円未満のもの
- 原状回復のために行われたもの
- 工事費用が20万円を超えているが、3年以内に定期的に行っているもの
- 災害で被害を受けた箇所の原状回復のために行われたもの
リノベーションの減価償却の具体的な考え方
減価償却の対象となる資産は、建物だけではなく、室内外の設備や機械装置なども対象となります。
つまり、リノベーション工事の際に住宅設備などを交換していればそれらも減価償却の対象となります。
先ほど説明した「修繕費」は原状への回復を目的としている為、工事によって価値が向上したとは判断されず、減価償却の対象とはならないため、工事が終了した年に一括経費計上することになります。
室内設備の「耐用年数」
耐用年数とは、その固定資産が「どれくらい使えるのか」という期間を指します。
減価償却の対象となる建物や設備には法定耐用年数というものが定められており、その耐用年数に則り減価償却ができる年数が定められています。
リノベーションを行った際に交換した室内設備も建物同様に減価償却の対象となります。
建物附属設備の耐用年数例
| 冷房用・暖房用機器 | 6年 |
| インターホン | 6年 |
| 照明設備 | 15年 |
リノベーション費用の減価償却計算方法
先ほども登場しましたが、減価償却の計算方法は、「定額法」と「定率法」の2種類があります。
資産の種類ごとに使える方法は決まっており、建物は「定額法」で計算することが決まっていますが、建物附属設備のリノベーション費用は、「定率法」で計算することも可能です。
(定額法で計算することも可能です。)
【建物】定額法の計算方法
「リフォーム費用×定額法の耐用年数に応じた償却率」と計算します。
例えば、木造の建物を100万円で改装工事を行ったとします。
木造の耐用年数22年では償却率0.046と定められているため、100万円×0.046=46,000円となり、年間46,000円の減価償却費を計上することになります。
(参照)減価償却資産の償却率表|国税庁
【建物付属設備】定率法の計算方法
「(リフォーム費用-償却累計額)×定率法の耐用年数に応じた償却率」と計算します。
例えば、100万円で共用部の照明設備交換工事を行ったとします。
照明設備の耐用年数は15年なので償却率は0.133です。償却年が1年目だとすると、
(100万円-0)×0.133=133,000円となります。
(参照)減価償却資産の償却率等表|国税庁
それぞれのメリット・デメリット
定額法のメリットは、計算方法がシンプルで、定率法より初期の減価償却費が少ないため初期の費用を抑えることができます。
逆に定率法に比べ、資産の収益力が低下し保守費等がかさむ後年になると負担比率が高くなる点があります。
定率法のメリットは、早い段階で費用計上できますので、投資額の資金回収を早めることができます。
しかしながら年数が経つにつれて節税効果が薄れ、また、初期段階の償却負担が重く利益を圧迫する可能性もあります。
節税効果の具体例
減価償却が注目される最大の理由は、節税効果の大きさにあります。
実際の支出を伴わない費用を計上できるため、税金の負担を抑えつつキャッシュフローを改善できるのです。
特に高所得者や法人にとっては、課税所得を圧縮する効果が顕著であり、実際の数値シミュレーションを通じて理解すると、その有効性が一層わかりやすくなります。
ケーススタディ:サラリーマン投資家の場合
仮に、年収800万円のサラリーマンが、築20年の木造アパート(購入価格5,000万円、うち建物価格3,000万円)を購入したケースを考えてみましょう。
前述の計算ルールから、このアパートの新耐用年数は6年となります。
つまり、建物価格3,000万円を6年で償却するため、年間の減価償却費は約500万円 となります。
この減価償却費は、実際の支出を伴わない経費として認められます。
したがって、家賃収入から経費を差し引いた後の所得からさらに500万円を控除でき、課税所得を大幅に減らすことができます。
仮にそのサラリーマンの課税所得が800万円だったとすると、減価償却を適用することで課税所得は300万円に圧縮されます。
結果として、所得税・住民税を合わせて100万円以上の節税効果が得られる可能性があります。
キャッシュフローへの影響
減価償却の大きなメリットは、「実際の支出がないのに経費にできる」点です。
上記の例では、家賃収入はそのまま手元に残りつつ、帳簿上は500万円の費用を計上できます。
これにより、税負担を軽減しながら、手元に資金を厚くすることが可能になります。
たとえば、
-
家賃収入:600万円
-
実際の経費(修繕費や管理費など):200万円
-
減価償却費:500万円
とすると、帳簿上の所得は「600−200−500=▲100万円」となり、赤字扱いになります。
しかし実際には400万円(=600−200)のキャッシュフローが手元に残るのです。
法人経営者のケース
法人経営者にとっても減価償却は有効です。
法人の利益を圧縮することで法人税の負担を軽減でき、節税効果を享受できます。
さらに、法人の資金繰りを安定させ、次の事業投資や借入返済に充てることが可能になります。
ただし、法人の場合は会計処理や金融機関との関係も絡んでくるため、個人投資家以上に慎重な設計が求められます。
節税効果のまとめ
-
減価償却は「見えない経費」であり、現金を伴わずに課税所得を圧縮できる。
-
中古物件、とくに法定耐用年数を超えた築古物件では、短期間で大きく償却できるため節税効果が大きい。
-
高所得者や法人が不動産投資を活用する理由のひとつは、まさにこの「減価償却による節税効果」にある。
減価償却の注意点とデメリット
減価償却は不動産投資における強力な節税ツールですが、万能ではありません。
短期的に税負担を減らす効果がある一方で、将来的な売却益の増加や融資審査への影響など、見落としがちなリスクも存在します。
ここでは、投資家が特に注意すべきポイントを整理します。
売却時に譲渡所得が増える可能性
減価償却によって建物の簿価(帳簿上の価値)は年々減っていきます。
これは会計上当然の処理ですが、将来物件を売却する際には注意が必要です。
譲渡所得は「売却価格 −(取得費 − 減価償却累計額)− 諸経費」で計算されます。
つまり、減価償却を多く取れば取るほど簿価が小さくなり、その分「売却益」が大きくなってしまうのです。
例えば、3,000万円の建物を6年間で全額償却した場合、簿価はゼロになります。
その後に2,000万円で売却すると、売却益は丸ごと2,000万円として課税対象になるのです。
短期的な節税が、将来的な税負担増につながる点は見落とせません。
銀行融資の評価に影響する
減価償却は帳簿上の費用であるため、利益を圧縮します。
節税という観点ではメリットですが、金融機関の融資審査においては「赤字決算」と見なされるリスクがあります。
特に法人での投資では、減価償却によって大幅な赤字を計上すると「収益性の低い会社」と評価され、新規融資や借換えの審査に悪影響を及ぼすことがあります。
金融機関によっては「減価償却費を加味して実質収益を評価する」ケースもありますが、必ずしもすべての銀行が柔軟に対応してくれるわけではありません。
税務調査リスクへの注意
中古物件の購入時には、建物と土地の価格割合をどのように設定するかが重要です。
建物部分を大きく見積もれば減価償却額を増やせますが、不自然な配分をすると税務署から指摘される可能性があります。
また、リフォーム費用の処理についても注意が必要です。
「修繕費」として一括経費にできるのか、「資本的支出」として減価償却に回すべきか、判断を誤ると後々の税務調査で修正申告を求められるケースもあります。
キャッシュフロー偏重の落とし穴
減価償却の魅力はキャッシュフローを厚くできることですが、それだけに依存するのは危険です。
税金の負担が少ないからといって修繕積立や空室リスク対策を怠れば、将来的に大きな出費に耐えられなくなります。
短期的な節税効果と、長期的な物件運営のバランスを常に意識することが重要です。
減価償却をめぐる典型的な誤解
投資を始めたばかりのオーナーに多い誤解として、
-
「減価償却は現金収支と直結している」
-
「償却が終わると投資の旨味がなくなる」
といったものがあります。
実際には、減価償却は会計上の処理であり、直接的に現金が動くわけではありません。
また、償却が終わったからといって投資の魅力がゼロになるわけではなく、むしろ「税金を払う余力ができる=次の投資に進める段階」と捉えることも可能です。
押さえておきたい減価償却の落とし穴
減価償却は強力な武器である一方、その効果を享受するタイミングや将来の影響を誤解すると、思わぬ税負担や融資トラブルに直面しかねません。
重要なのは「短期の節税メリット」と「長期の資産戦略」のバランスを意識し、適切にコントロールすることです。
節税だけじゃない、長期戦略としての減価償却
減価償却は、不動産投資における節税・キャッシュフロー改善の強力なツールです。
建物の構造や築年数、物件タイプによって償却額や期間が変わるため、投資戦略に応じて計画的に活用することが重要です。
ただし、短期的な節税効果だけに目を奪われると、将来の売却益の増加や融資審査、税務調査のリスクを見落としがちです。
個人・法人それぞれの立場に応じた設計と、専門家のサポートを受けながら、長期的なキャッシュフローと資産形成のバランスを意識することが、成功する不動産投資の鍵となります。
減価償却を正しく理解し、賢く活用することで、安定した賃貸経営と資産形成を両立させることが可能です。
このコラムの内容を参考に、計画的な投資戦略を立ててみてください。