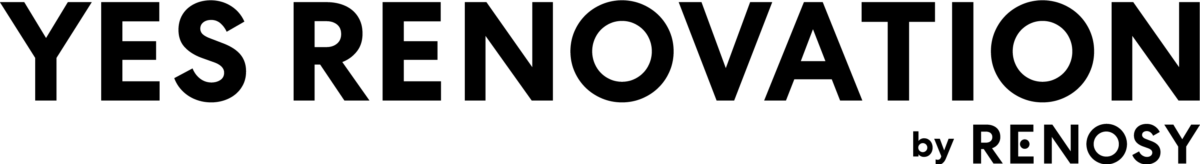2025年地価速報|一都三県の最新動向と賃貸オーナーがやるべきこと

2025年地価速報|一都三県の最新動向と賃貸オーナーがやるべきこと
2025年9月16日、国土交通省から最新の基準地価(2025年7月1日時点)が発表されました。
全国平均は前年比+1.5%と4年連続の上昇。
特に三大都市圏は+4.3%と全国を大きく上回り、バブル期以来の力強い伸びを示しました。
ニュースや新聞でも「銀座の地価が1㎡あたり4,690万円」「北海道千歳市が全国最高の上昇率」といった話題が取り上げられています。
しかし、こうした全国的な数字以上に重要なのは、オーナー自身が所有する地域の地価がどう動いているかです。
なぜなら、地価の動きは――
-
保有物件の資産価値
-
金融機関の融資評価
-
将来の相続・売却時の価格形成
-
さらには固定資産税や相続税の負担
といった形で、賃貸経営に直接影響を及ぼすからです。
本コラムでは、その中でも賃貸物件オーナーが多く物件を保有する 一都三県(東京・神奈川・千葉・埼玉)の住宅地 に焦点をあて、地価動向と賃貸経営への示唆を解説していきます。
一都三県の住宅地地価の最新動向
首都圏の住宅地は、全国的にも突出した強さを示しています。
全国平均がプラス基調にある中で、一都三県はその牽引役を果たし、特に利便性の高いエリアや再開発が進む地域で大幅な上昇が確認されました。
逆に、人口減少や需要停滞の影響を受けやすい郊外エリアでは横ばいから下落の動きも見られ、二極化が顕著になっています。
オーナーにとっては、物件の立地によって今後の経営戦略が大きく変わる局面といえるでしょう。
東京:都心部は依然として高値、郊外も堅調
東京都は依然として全国をリードする存在です。
特に中央区、港区、渋谷区といった都心部では、オフィス需要と住宅需要が重なり、地価の押し上げ要因となっています。
渋谷駅周辺や虎ノ門・麻布台地区の大規模再開発は住宅市場にも波及しており、投資対象としての人気を後押ししています。
さらに、城南エリアや城西エリアでも住宅地の上昇が目立ち、世田谷区や目黒区の住宅地は安定した人気を維持しています。
一方で、都心から距離のある多摩地域の一部では横ばい傾向も見られ、利便性の差が地価に直結しています。
神奈川:横浜・川崎は堅調、西部は二極化
神奈川県では、横浜市と川崎市の上昇が際立ちます。
特に横浜みなとみらい地区や川崎駅周辺は、再開発と交通アクセスの改善が相まって地価の伸びが続いています。
武蔵小杉エリアも引き続き人気で、タワーマンション群が地域の象徴となっています。
東京に隣接する川崎市北部や横浜市港北区は、都心通勤圏としての安定感からファミリー層を中心に需要が高止まりしています。
一方、県央や西部地域では上昇の勢いは弱く、相模原市や小田原市などでは横ばいまたは微減の傾向が確認されました。
千葉:湾岸エリアは人気、内陸は慎重
千葉県は、東京湾岸エリアの強さが際立っています。
浦安市や市川市、船橋市などは東京へのアクセスが良く、都心の住宅価格高騰を背景に需要が流入しています。
また、幕張新都心エリアも再開発や商業施設の充実によって人気が高まっています。
加えて、東京ディズニーリゾートの存在がブランド力を押し上げ、周辺地価にプラスの影響を与えています。
これに対して、県北部や房総半島の内陸部では人口減少の影響が色濃く、需要の減退により地価は横ばいから下落が目立ちます。
埼玉:大宮・川口・浦和は堅調、外縁部は注意
埼玉県は、東京のベッドタウンとしての位置づけが強く、ターミナル駅周辺の上昇が目立ちます。
特に大宮駅、浦和駅、川口駅の周辺は、都心直結の利便性と商業集積が相まって人気が集中しています。
大宮駅は新幹線の停車駅としての利便性、浦和駅は文教都市としてのブランド力、川口市は都内に隣接する立地が評価され、いずれも住宅需要を強力に押し上げています。
さいたま新都心エリアも行政機能や商業施設の集積により存在感を高めています。
ただし、県北部や秩父方面などでは需要減少が避けられず、地価は横ばいから下落傾向が続いています。
地価上昇が賃貸経営に与える影響
地価の上昇は、賃貸物件オーナーにとってプラス面とマイナス面の両方をもたらします。
資産価値が高まる一方で、固定資産税の負担増や相続税評価額の上昇といったリスクも同時に発生します。
また、金融機関の融資評価や賃料設定の根拠にも直結するため、数字を冷静に読み解くことが重要です。
固定資産税・都市計画税の負担増
地価が上昇すると、土地の固定資産税評価額も上がります。
たとえば評価額が1億円から1億1,000万円に上昇した場合、1.4%の固定資産税率で計算すると年間14万円程度の税負担増になります。
さらに都市計画税(0.3%程度)が加われば、実質的なキャッシュフローの圧迫につながります。
オーナーにとっては大きな出費ではないと感じるかもしれませんが、複数物件を所有している場合や、すでにローン返済・修繕費がかさんでいる経営状況では軽視できない影響となります。
金融機関による融資評価
一方で、地価上昇は金融機関の評価を高める要因になります。
担保価値が上昇することで、借り換えや追加融資の交渉がしやすくなります。都市銀行は担保評価にシビアですが、地価の堅調な都心部やその周辺エリアであれば積極的に資金を出す傾向があります。
地方銀行や信用金庫では、地元エリアの評価に基づき融資枠が広がる可能性があります。
たとえば築20年以上のマンションでも、立地が良ければ「修繕資金の追加融資」や「低金利ローンへの借り換え」が実現するケースもあります。
オーナーにとっては、資金繰り改善や新規投資のチャンスを広げる好機です。
賃料設定への影響
地価上昇は、新築物件の建築コストや仕入れ価格の上昇を意味します。
そのため、既存物件の家賃水準を維持・上昇させやすい環境が整います。
ただし、実際に賃料を引き上げられるかどうかはエリアの需給バランス次第です。
たとえば都心部では「新築が高すぎて借りられない層」が中古賃貸に流れ込むため、家賃上昇の追い風となります。
一方、郊外や人口減少エリアでは地価が横ばいでも入居者数が伸び悩み、賃料を上げるどころか現状維持すら難しい場合もあります。
オーナーにとっては「単に地価が上がったから家賃を上げる」という短絡的な判断は危険で、周辺相場や新築供給動向を綿密にチェックすることが欠かせません。
収益シミュレーションの重要性
これらの要素を総合すると、オーナーが今すぐ取り組むべきは「収益シミュレーションの見直し」です。
固定資産税や修繕費の増加を織り込みつつ、賃料上昇や融資条件改善をどう活かすかを数字で確認する必要があります。
特に複数物件を持つ場合は「どの物件が安定収益を生み、どの物件がリスク要因になるか」を洗い出すことが経営戦略の第一歩です。
地価上昇がもたらす税負担・融資環境の変化
地価の上昇は、資産価値の増加というメリットをもたらす一方で、賃貸オーナーにとっては「税負担」と「融資環境」という二つの側面で無視できない影響を与えます。
特に一都三県の住宅地は評価額の上昇が反映されやすいため、経営に直結する課題となります。
固定資産税・都市計画税の増加リスク
地価が上昇すると、自治体が課税基準とする「固定資産評価額」に影響が及び、結果として固定資産税や都市計画税の負担が増加する可能性があります。
たとえば、評価額が1割上昇すれば、年間数万円単位で税負担が増えるケースも珍しくありません。
築年数が経過して建物価値が下がっても、土地部分の評価額が上がればトータルの課税額は増えるため、長期的にはキャッシュフローを圧迫します。
オーナーにとって重要なのは、「税負担の変動を見越した資金計画」を立てておくことです。
特に複数棟を所有している場合や、土地面積が広い物件を保有している場合には影響が大きいため、税理士や不動産会社と連携して事前にシミュレーションしておくべきです。
相続税評価額の上昇と対策
もう一つの影響は相続税です。地価の上昇は「路線価」や「相続税評価額」にも反映され、相続税の負担を重くします。
たとえば東京23区や横浜市内の人気エリアでは、路線価が前年比で2~3%上昇するケースもあり、数千万円単位で評価額が膨らむ可能性があります。
この場合、賃貸オーナーが取るべき対策は以下の通りです。
-
法人化の検討:個人名義ではなく法人での所有に切り替えることで、相続時の評価や課税方法を調整できる。
-
生前贈与の活用:暦年贈与や相続時精算課税制度を利用して、早めに資産移転を進める。
-
不動産の組み替え:資産価値が過大に膨らんでいる土地を一部売却し、利回りの高い物件や地方物件に振り替える。
単に「相続税が増えるかもしれない」で終わらせず、実際の資産承継戦略に組み込むことが、長期的に見て大きな差を生みます。
融資環境への影響
地価の上昇は、金融機関の融資姿勢にも影響します。
一般的に、担保評価額が高まれば追加融資や借り換えがしやすくなる一方で、金融庁の監督強化や市況悪化によって融資姿勢が引き締まる場合もあります。
オーナーが押さえておきたいのは、
-
借り換えタイミングの見極め:地価が高い時期は担保評価が出やすいため、低金利の金融機関への借り換えを検討する好機。
-
修繕資金の確保:担保余力があるうちに修繕やリノベーション資金を確保し、物件の競争力を維持する。
-
自己資本比率の向上:地価上昇に浮かれて過剰借入をせず、長期的な経営の安定を優先する。
融資環境は景気や金利動向に大きく左右されるため、地価上昇による追い風を一時的なものと捉え、慎重に活用することが肝要です。
エリア別オーナー戦略
地価の上昇・停滞傾向はエリアごとに異なり、それに応じた賃貸経営の戦略が必要です。
単純に「地価が上がったから安心」というわけではなく、入居者の動向や供給状況を踏まえた柔軟な対応が求められます。
東京23区
東京23区では、依然として都心部を中心に強い需要が続いています。
特に中央区や港区、渋谷区などの高級住宅地では、築古物件であっても立地の魅力が強く、リノベーションを行うことで十分に競争力を確保できます。
また、賃料水準も上昇傾向にあり、修繕や改装投資を行っても回収の目途が立ちやすい環境です。
一方で、城東・城北エリアでは価格帯が比較的抑えられる分、入居者層の幅が広く、差別化のためには「設備面の充実」「管理品質の向上」がポイントとなります。
神奈川エリア
横浜・川崎は依然として人気が高く、東京へのアクセスの良さから賃貸需要も堅調です。
これらのエリアでは、都内に比べて物件価格がやや抑えられるため、利回りを確保しやすい特徴があります。
ただし、県央や西部(相模原・小田原など)では、地価は横ばいか微減となっており、空室リスクが高まりやすい傾向にあります。
オーナーとしては「賃料を抑える」よりも「付加価値を高める」ことで入居者を確保する戦略が有効です。
千葉エリア
千葉では、湾岸エリア(浦安・市川・船橋など)を中心に地価の上昇が続いています。
都心へのアクセスが良く、ファミリー層のニーズが根強いのが特徴です。
一方で、内陸部や外房・内房方面では需要が限定的で、人口減少の影響が早く現れやすいエリアでもあります。
こうした地域では「低価格帯での安定入居」を狙うか、「特色のあるコンセプト賃貸」を導入して差別化を図る必要があります。
埼玉エリア
大宮・浦和・川口といったターミナルエリアは、都心への通勤需要を背景に堅調な上昇を続けています。
東京と比べて家賃水準が抑えられているため、入居希望者が安定しており、長期保有に適した市場といえるでしょう。
一方で、外縁部(秩父や北部エリア)では人口減少の影響が強く、賃貸需要は減少傾向にあります。
このため、空室対策や賃料設定の見直しが欠かせません。
相続・資産戦略への影響とオーナーが取るべき行動
地価の上昇は「いまの収益」に直結する固定資産税だけでなく、将来的な「資産承継」にも大きな影響を与えます。
特に一都三県の住宅地は相続税評価額が上昇しやすく、オーナーにとって無視できない課題となっています。
ここでは相続税の仕組みから具体的な対策まで整理します。
相続税評価額の上昇リスク
相続税は「路線価」をもとに算定されます。
路線価は公示地価の約8割程度が目安とされており、地価が上がれば路線価も追随する傾向にあります。
たとえば、2025年に路線価が前年比3%上昇したエリアでは、土地の評価額が1億円なら+300万円評価されることになります。
この評価額は相続税計算にそのまま影響するため、相続税負担が数十万円〜百万円単位で増えることも珍しくありません。
加えて、複数の物件を所有している場合は評価額の合計が大きく跳ね上がるため、「課税対象者ではなかったはずが、いきなり相続税課税の範囲に入ってしまう」というケースも考えられます。
賃貸物件の評価減を活用する
一方で、賃貸物件には「貸家建付地」としての評価減ルールがあり、これを活用すれば相続税評価額を圧縮できます。
入居率が高く、安定的に賃貸経営が行われている物件ほど評価減の効果が出やすいため、日頃の賃貸管理が相続対策にも直結します。
-
貸家建付地の評価減:自用地より20〜30%程度評価を下げられる。
-
小規模宅地等の特例:居住用または事業用の土地について最大80%の評価減が可能。
これらを組み合わせることで、評価額を大幅に下げることができ、相続税の負担を軽減できます。
生前贈与・法人化の活用
オーナーが早めに検討すべきなのは「資産をどう分散・移転するか」です。
-
生前贈与:暦年贈与を活用すれば、毎年110万円まで非課税で贈与できます。また、相続時精算課税制度を用いれば2,500万円まで贈与可能(ただし将来相続に加算)。
-
法人化:物件を法人に移し替えることで、相続税や所得税の圧縮、管理の効率化につながる。法人で利益をプールすれば、修繕や新規投資にも柔軟に使える。
ただし、法人化には移転時の不動産取得税や登録免許税、譲渡所得税といったコストがかかるため、シミュレーションが不可欠です。
売却・組み替えによる戦略的対応
地価が高い今だからこそ「売却して現金化」「郊外や地方物件への組み替え」を検討するのも有効です。
-
相続人が複数いる場合には、分割のしやすい形に資産を整理しておく。
-
資産を流動化しておくことで、納税資金を確保しやすくする。
このように、相続は「税負担を減らす」だけでなく「相続人同士の争いを防ぐ」という側面も大切です。
オーナー自身の判断だけでなく、家族や専門家と協議しながら最適な資産戦略を描くことが重要になります。
専門家との連携が成功の鍵
相続や資産承継の問題は、法律・税務・不動産の知識が交差する高度な領域です。
税理士や弁護士、不動産コンサルタントと早めに連携し、自分のポートフォリオに合わせた最適解を見つけることが成功のカギを握ります。
特に、近年は「不動産特化型の税理士」や「相続に強い不動産会社」も増えているため、専門家選びも経営戦略の一部と考えるべきでしょう。
地価動向を経営戦略に活かす視点
2025年の地価発表では、一都三県の住宅地が総じて上昇傾向を示しました。
これは賃貸オーナーにとって資産価値の裏付けとなる一方、固定資産税や相続税といった負担増のリスクも孕んでいます。
東京23区や横浜・川崎、大宮・川口といった都市部では賃貸需要が引き続き堅調であり、築古物件でも適切な投資を行うことで競争力を維持できます。
逆に、郊外や人口減少が顕著なエリアでは、入居者確保の工夫が不可欠です。
オーナーが取るべき行動は、地価の数字を「単なる市場の話題」として受け止めるのではなく、経営判断の指標 として積極的に活用することです。
借り換えや修繕計画、売却・入れ替え、相続対策など、地価動向を前提にした戦略を描くことで、賃貸経営の安定と拡大を実現できます。